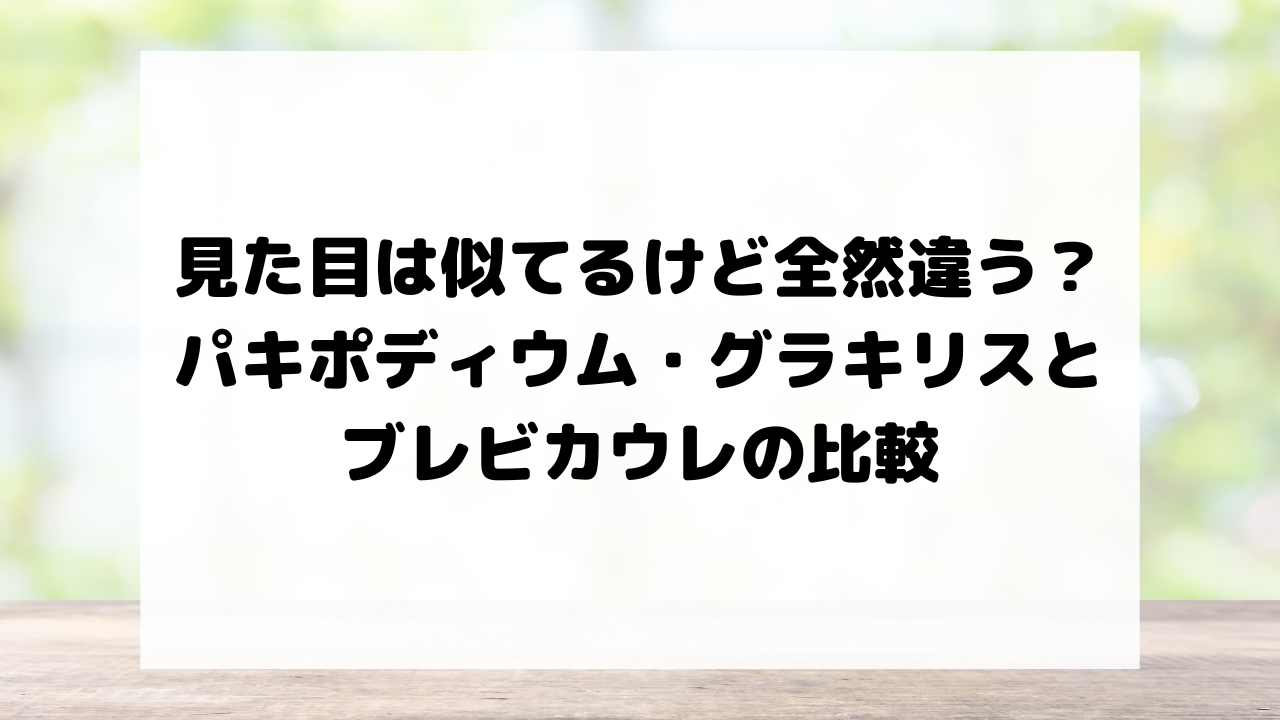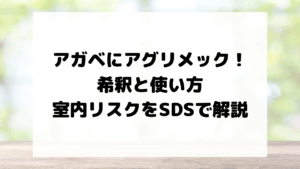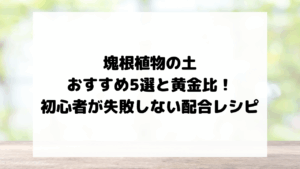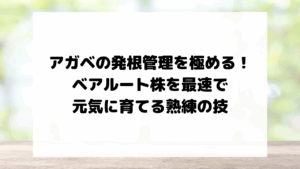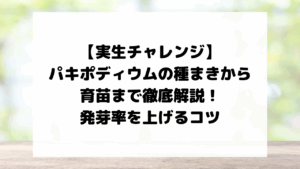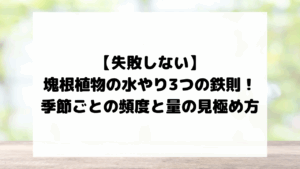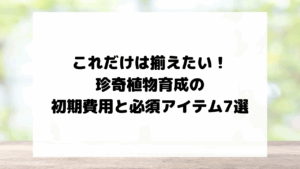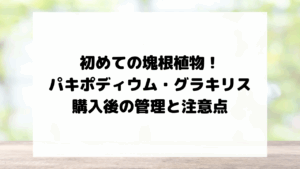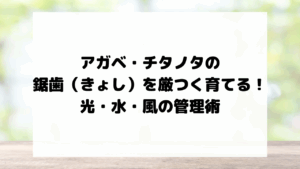まん丸に、あるいは岩のようにゴツゴツと膨らんだ塊根部。パキポディウムの世界に足を踏み入れた者が、まず最初に憧れるのが、この低重心でどっしりとしたフォルムを持つ「グラキリス」や「ブレビカウレ」ではないでしょうか。
「あれ、この二つって何が違うの?」
「小さい株だと、正直見分けがつかない…」
こんにちは!塊根植物の育成記録を発信している、ヒロセです。
その気持ち、非常によくわかります。特に園芸店で小さな苗が並んでいると、一見しただけでは判別が難しいこともありますよね。しかし、私のコレクションで両者を長年育ててきた経験から言うと、この二つは似て非なる、全く個性も性格も違う植物です。
この記事では、しばしば混同されがちな二大巨頭、グラキリスとブレビカウлеを徹底的に比較し、見分け方のポイントから、実はかなり違う「育て方」のコツまで、私の実体験を交えながら詳しく解説していきます。
なぜグラキリスとブレビカウレは混同されやすいのか?

両者ともにマダガスカル原産であり、乾燥した岩場に自生しています。似たような環境で育つため、水を蓄えるために塊根部が丸く、低く育つという、似通った姿に進化したと考えられています。特に、野球ボールくらいのサイズまでの幼株は、特徴が出にくく、見分けるのが困難な場合があります。
しかし、それぞれの特徴を理解すれば、その違いは明確です。コレクターとして、その差を見極める「眼」を養っていきましょう。
【徹底比較】グラキリス vs. ブレビカウレ 見分け方のポイント

私が実際に見分ける際に注目している、4つの大きなポイントをご紹介します。
見分けポイント①:肌の色と質感
グラキリスの肌
若いうちは緑がかっていますが、成長するにつれて黄褐色〜象牙色のような、滑らかな質感の肌になります。太陽によく当てて育てると、美しい艶を帯びてきます。
ブレビカウレの肌
和名「恵比寿笑い」の名の通り、どこか古びた仏像のような、ざらつきのある銀灰色〜白っぽい肌をしています。グラキリスに比べて、より岩石に近い、ゴツゴツとした質感です。
見分けポイント②:株の形状
グラキリスの形
幼株のうちは丸いですが、成長するにつれて縦方向へと伸び、徳利(とっくり)のような「首」を形成していきます。上へ上へと伸びていく力強さ、生命力を感じさせるフォルムです。
ブレビカウレの形
成長しても背は高くならず、横方向へと扁平に広がっていきます。まさに「お饅頭」のような形で、地面を這うように、どっしりと構えるのが特徴です。この横への広がりが、ブレビカウレの最大の魅力とも言えます。
見分けポイント③:葉の形と特徴
グラキリスの葉
比較的、細長くシャープな葉をしています。色は鮮やかな緑色で、表面には光沢があります。
ブレビカウレの葉
グラキリスよりも幅が広く、丸みを帯びたヘラのような形をしています。葉の表面には細かい毛が生えていることが多く、そのために少し白っぽく、マットな質感に見えます。
見分けポイント④:花の色(※決定的な違い)
もし花が咲けば、その違いは一目瞭然、100%確実に見分けることができます。
グラキリスの花
鮮やかで、目の覚めるような黄色い花を咲かせます。
ブレビカウレの花
クリーム色がかった、淡い黄色の花を咲かせます。グラキリスに比べると、明らかに白っぽい花です。
【ヒロセの体験談】
私も最初は葉や形で判断していましたが、やはり個体差もあって悩むことがありました。しかし、一度両方の花を自分のコレクションで咲かせた時、その色の違いに「なるほど、こういうことか!」と深く納得しました。花は、彼らが発する最も正直な自己紹介ですね。
育て方は同じでOK?栽培上の違いと注意点

見た目以上に、日々の管理で注意すべき点にも違いがあります。同じ感覚で育てていると、思わぬ失敗を招くことがあります。
成長速度:グラキリスは意外と速い
私の環境下での体感ですが、同じくらいの大きさの株であれば、グラキリスの方がブレビカウレよりも成長は早いです。特にカキ仔のグラキリスは、適切な管理をすれば目に見えて大きくなっていきます。ブレビカウレは、よりゆっくりと、時間をかけてその風格を増していく印象です。
水やり:ブレビカウレはより「根腐れ」に注意!
これが栽培における最大の違いであり、最重要ポイントです。
ブレビカウレは、グラキリスに比べて、明らかに根腐れしやすいです。その理由は、あの扁平なフォルムにあります。株が蓋のように用土を覆ってしまうため、土中の水分が乾きにくいのです。
【ヒロセの育成メモ】
私は、ブレビカウレに使う用土は、グラキリス用よりもさらに軽石などの割合を増やし、極限まで水はけを良くしています。水やりも、グラキリスなら「用土が乾いてから3日後」のところを、ブレビカウレは「乾いてから1週間後」というように、より厳しく、辛めに管理しています。この差が、ブレビカウレを健康に夏越しさせる秘訣だと感じています。
耐寒性:どちらも寒さは苦手だが…
両種ともに冬は休眠し、寒さに弱いですが、これも私の体感では、ブレビカウレの方がより低温や冬の湿気に弱いように感じます。冬場は完全に水を切り、室内のできるだけ暖かい場所で管理するのが安全です。
まとめ:似て非なる二つの巨頭、その個性を楽しもう
パキポディウム・グラキリスとブレビカウレ。一見似ているようで、その実、
- 肌は、象牙色のグラキリス、岩石質のブレビカウレ
- 形は、縦に伸びるグラキリス、横に広がるブレビカウレ
- 育てやすさは、比較的タフなグラキリス、より繊細なブレビカウレ
という、明確な個性を持った、全く別の植物です。
どちらか一方を育てるのももちろん楽しいですが、両方をコレクションに加えて、その違いを日々観察することで、パキポディウムという植物の奥深さを、より一層感じることができるはずです。
この記事が、あなたの株選びと、その後の栽培の参考になれば幸いです。